Appleが初めて自社開発したモデムチップ「C1」。でも、よく見るとミリ波5Gに対応していないんです!
「え、なんで?」と思った人も多いはず。でも実は、これにはちゃんとした理由があるんです。
Appleお得意の低消費電力設計が裏目に⁉︎ その理由と今後の展開について、わかりやすく解説します!
C1チップ開発の苦労話!モデムチップってそんなに大変なの?
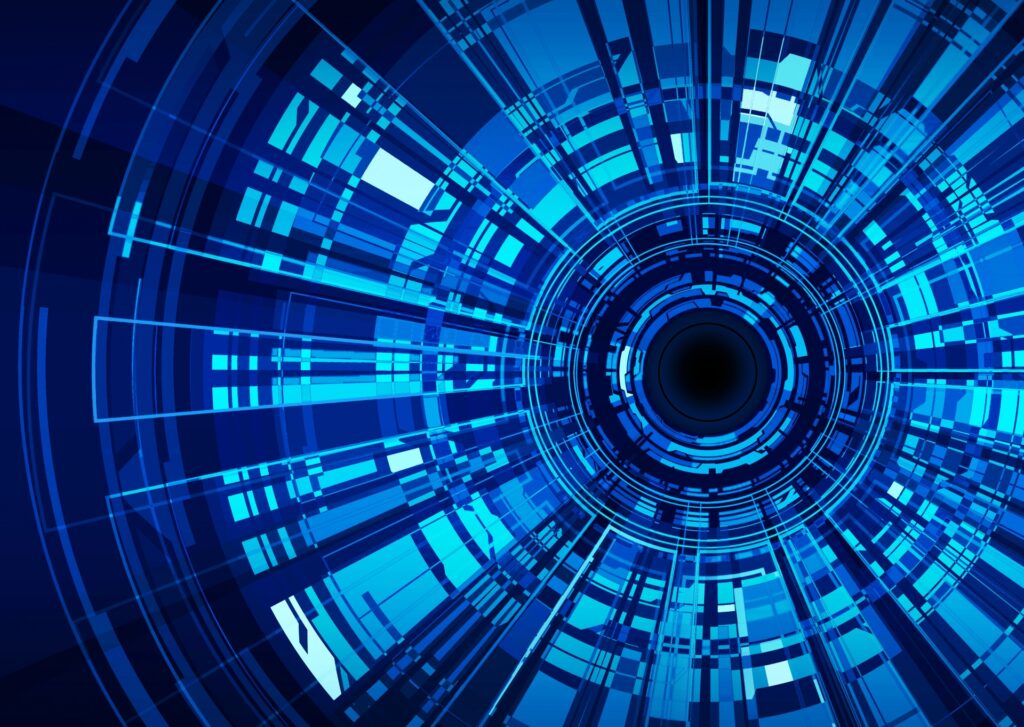
Appleが開発したC1チップ、これ実はめちゃくちゃ大変なプロジェクトだったんです。だって、スマホの「脳みそ」みたいなプロセッサとは違って、モデムチップは世界中の通信規格に対応しないといけません。
例えば、日本とアメリカでも使っている電波が違うし、キャリアによっても周波数や通信方式がバラバラ。さらに、5Gだけじゃなくて、4Gや3G、場合によっては2Gにも対応しないといけないんです。「電波がないから3Gに落ちる」なんて経験、ありますよね? それをスムーズにやるために、C1はあらゆる通信方式を詰め込む必要があったんです。
AppleはMac用のMシリーズチップで「Intelなんかいらん!」ってレベルの成功を収めましたが、モデム開発はそんなに甘くないんです。データ通信の世界はめちゃくちゃ複雑で、ちょっとのズレで通信が不安定になったり、電池消費が爆増したりするんですよ。だから、C1の開発には何年もかかったんです。
それに、Appleは「デザイン重視」の会社です。チップのサイズが大きくなりすぎると、iPhoneのデザインに影響するし、消費電力が増えたらバッテリー持ちが悪くなる。そういう制約の中で、できるだけ優れたモデムを作るのは本当に大変な作業なんです。
じゃあ、なぜミリ波5Gを切り捨てたのか? 次のセクションで、その理由を深掘りしていきます!
Appleが選んだ2つの妥協点…ミリ波5GとWi-Fi 7はナシ!
AppleのC1チップには、2つの大きな妥協がありました。それが「ミリ波5G非対応」と「Wi-Fi 6止まり」なんです。でも、なんで最新技術をバッサリ削ったんでしょう?
まず、ミリ波5Gって、超高速で通信できる夢のような技術なんですが、実は使える場所がめちゃくちゃ限られているんです。基本的に、都市部の一部エリアとか、スポーツスタジアムみたいな特定の場所でしか意味がありません。それに、ミリ波対応のモデムは消費電力がめちゃくちゃ高くなるので、iPhoneのバッテリー持ちに影響しちゃいます。
Appleのアプローチは「必要ないなら省く」。この割り切りがC1にも適用されました。確かに、ミリ波対応すればスペック的には豪華になりますが、バッテリーをゴリゴリ消費する割に使える場面が少ないなら、いっそ切っちゃおうという判断だったわけです。
もう一つの妥協点が「Wi-Fi 7非対応」です。これも同じ理由で、省電力のためにWi-Fi 6で止めてるんですね。Wi-Fi 7はまだ普及していないし、iPhoneユーザーの大半が違いを体感できるほどの環境にいないので「とりあえず次のモデルで対応すればいいか」という感じでしょう。
結局のところ、Appleは「今、本当に必要な機能か?」を考えて、C1チップの仕様を決めたんです。では、次のC1はどうなるのか? 次世代モデルの展望を見ていきましょう!
次世代C1はどうなる?ミリ波対応に向けたアップルの挑戦
さて、ミリ波5Gは見送られましたが「永遠に対応しない」わけではありません。実は、Appleはすでに次世代のC1を開発中で、そこではミリ波5Gの対応を目指しているんです!
問題は「どうやって省電力と両立するか」。現在のミリ波モデムは消費電力が高く、iPhoneのバッテリーにとっては大敵です。Appleは「省エネで安定した通信」を目指して改良を進めているとのこと。もしかすると、独自の低消費電力技術を取り入れた新しいモデムが登場するかもしれません。
さらに、次世代C1ではWi-Fi 7にも対応する予定です。Wi-Fi 7は、通信の安定性や速度が飛躍的に向上するため、対応すればユーザーの体感速度もグッと上がるはず。Appleはこの新技術を活かして、より快適な通信環境を提供しようとしているんですね。
とはいえ、Appleのことなので「自社基準をクリアしないと搭載しない」方針は変わらないでしょう。なので、次世代C1がミリ波5Gに対応しても「Appleらしい省エネ&高性能」な形になっている可能性が高いです。
次のiPhoneでは、C1チップの進化によって通信環境がどう変わるのか、注目しておきたいですね!
Source:9to5Mac
